どうもじんでんです。今回は絶縁耐力試験における、充電電流についてまとめました。
絶縁耐力試験とは
電気設備は設置後に絶縁耐力試験を実施しなければなりません。
試験電圧や時間については、多くの方がご存知だと思います。しかし意外と知らないのが充電電流です。
これが分からないと、試験器の容量が足りずに絶縁耐力試験ができないということになります。今回は、6600V回路の絶縁耐力試験の充電電流の算出方法について説明していきます。
試験電圧や試験時間についてはこちらの記事を読んで下さい。
今回は交流電圧で試験の場合になります。直流電圧試験では違ってきますのでご注意下さい。
試験対象物は何か?
6600Vの高圧機器を絶縁耐力試験する場合、大きく3つに分けて充電電流の計算をします。各機器で計算が違ってくるので注意して下さい。
- 高圧ケーブル(CVケーブルやCV-Tケーブル)
- 変圧器
- その他の機器(断路器、遮断器、計器用変圧器、計器用変流器、コンデンサetc.)
高圧ケーブルの場合
充電電流で一番、注意しないといけないのがこの高圧ケーブルになります。それは充電電流が大きいからです。長さにやサイズでどんどん大きくなります。下記を参考に計算してみてください。
- 22(sq)・・・1.05(mA/m)
- 38(sq)・・・1.24(mA/m)
- 60(sq)・・・1.44(mA/m)
- 100(sq)・・・1.75(mA/m)
- 100(sq)・・・2.02(mA/m)
※60Hzで計算しています。
※1相分の電流値です。
小規模の受電設備であれば、38sqの20mぐらいで75mAになります。このくらいであれば全然問題ない範囲なのですが、距離が100mや200mとなると話が変わってきます。高圧ケーブルの充電電流は距離に比例するので、大きな工場などになると100m以上なんてよくある話なので注意が必要です。
高圧ケーブルの充電電流の計算はこちらの記事も参照ください。
変圧器の場合
変圧器は高圧ケーブルの次に充電電流が大きい機器です。しかしメーカーや機種により充電電流は様々ですし、カタログなどにも記載されていません。
私の今までの経験則だと、100kVAにつき10mAで計算すると良いでしょう。単相や三相は考えなくて大丈夫です。1台ずつではこの計算には当てはまらない場合もありますが、設備全体を見れば大体当てはまります。
しかし目安なので、大体と思って下さい。私の経験上、最近の変圧器は10mAよりも少ないと感じます。モールド変圧器はまだ低くなります。
その他の機器の場合
その他の機器ついては1個当たり1mAにも満たないので計算に考慮しなくて大丈夫です。
試験器の容量ってどのくらいあるの?
絶縁耐力試験をすることができる試験器は、色々なメーカーからでており容量も様々です。よく現場で見るのはムサシインテックのIP-R2000と組み合わせて使うR-1220ではないでしょうか。R-1220は容量は10350Vで200mAになります。変圧器だけなら2000kVAまで、高圧ケーブルの38sqなら約160mまでとなります。このように何か目安を持っておくといいですね。
しかし高圧ケーブルにしても変圧器にしても、天候や施工の状況で充電電流は変化するので余裕をもって準備しましょう。
まとめ
- 高圧ケーブルは充電電流が大きい。一覧表を参照して計算する。長いと要注意。
- 変圧器は100kVAあたり10mAで計算する。
- その他の機器は考慮しなくて大丈夫。
- 天候や施工状況で変化するので、試験器の容量は余裕をもって準備する。
今回は絶縁耐力試験の充電電流についてまとめてみました。
この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。











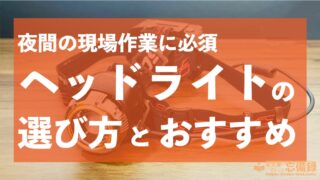

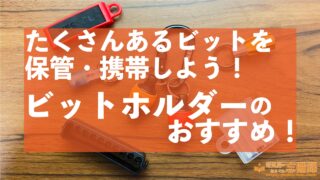

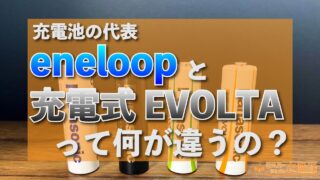


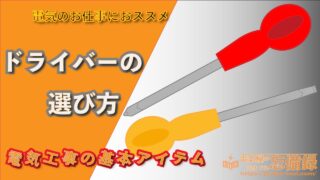


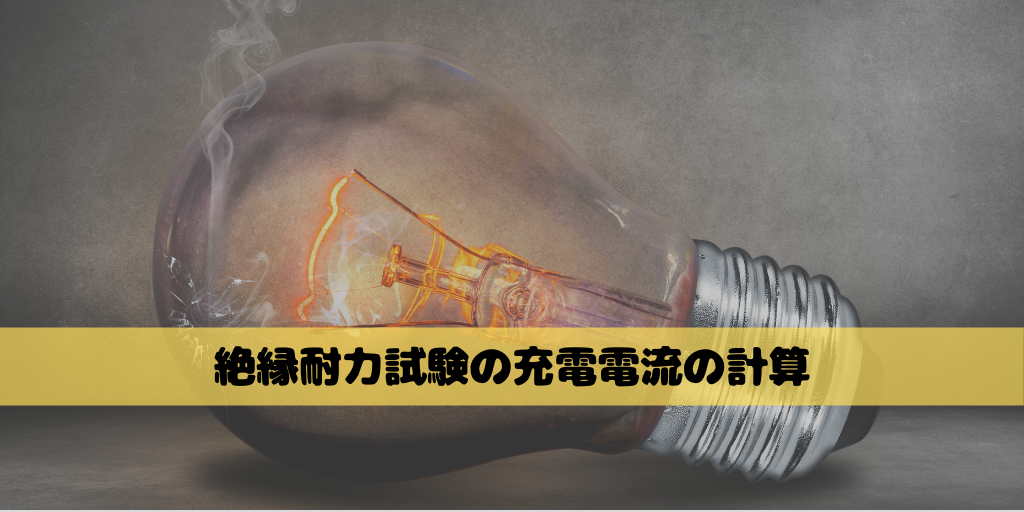
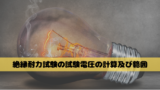
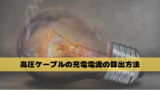







コメント
いつも拝見させていただいてます。
質問があります。
耐圧試験時に、ホンダの16i及び、9i発電機を持っていき試験をやっていますが、このたびホンダのポータブルE500を購入しまして、耐圧試験に使えるなら、軽量で排気の心配もないので助かるのですが、どれぐらいまでなら高圧ケーブル、高圧機器に対応できますでしょうか?
また、耐圧試験の際に、発電機を選定するにあたり、計算方法を教えていただければありがたいてす。よろしくお願いいたします。
いだてんさま
コメントありがとうございます。
発電機の容量の選定について解説します。
ムサシの試験機IP-R200とR-1220の組合せの場合は、試験用変圧器が2kVAです。
2kVAを試験電圧10350Vで割ると約193mAとなり、それが容量の限界となります。
これを一次側で考えると、2kVAを電源電圧100Vで割れば20A必要となります。
発電機も最低2kVA必要ですね。しかし裕度を考えるともう少し欲しいところです。
必要な発電機の容量は、試験時に流れる充電電流に比例するとお考え下さい。
E500は500VAなので、試験電圧10350Vで割ると約48mA位までは対応できそうですね。
48mAでどのくらいの被試験物に対応できるかは、サイトのページを参考にして下さい。
今回の計算は様々な諸条件を無視している理論上なので、実際は誤差があるかと思いますのでご注意下さい。
以上、よろしくお願い致します。