どうもじんでんです。今回は地絡継電器について記事にしました。地絡継電器(GR)は、特に高圧受電設備において重要な保護装置になります。よって様々な要素があり、まとめて全てを説明する事が難しいです。今回の記事は、基本的な事を簡単にまとめてみました。
地絡継電器は保護継電器の一種です。保護継電器の種類については、こちらをご覧ください。
地絡継電器(GR)とは?
地絡継電器(GR)は大きく2種類あり、無方向性と方向性に分けられます。
無方向性のものを地絡継電器と呼び、「GR」や「51G」とも表します。GRは「Ground Relay」の略称です。
方向性のものを地絡方向継電器と呼び、「DGR」や「67」とも表します。DGRは「Directional Ground Relay」の略称です。
「51G」及び「67」は日本電機工業会(JEMA)にて定められている「制御器具番号」に由来しています。
しかしこれら全ての総称で地絡継電器(GR)と呼ぶ事もあるので注意しましょう。
設置の目的
地絡継電器(GR)は名の通り、電路の地絡を検知して動作します。
高圧ケーブルや高圧機器の絶縁が劣化や破壊が起きたり、倒木による電線路への接触により地絡が発生します。
地絡が発生すると地絡電流が発生します。その地絡電流を零相変流器(ZCT)にて検知し、整定値を上回ると動作し開閉器や遮断器を開放します。
地絡を放置すると人への感電が発生する可能性があります。その為、瞬時に地絡点を電路より切り離さなければなりません。
地絡継電器(GR)は、需要家の責任分界点でもあるPASと組み合わせて設置される、SOG制御装置の一部としても機能しています。
SOG制御装置と地絡継電器(GR)は、よく混同されることがあります。SOG制御装置=地絡継電器(GR)と思われていたりもします。
正しくは、SOG制御装置の機能の1つとして地絡継電器(GR)が組み込まれています。なのでSOG制御装置と地絡継電器(GR)は別物と考えるのが良いでしょう。
SOG制御装置について詳しくは、こちらの記事で解説しています。併せてご覧ください。
構成機器
地絡継電器(GR)はそれだけでは動作する事ができず、地絡電流及び地絡電圧を検知する機器が必要になります。
地絡電流を検知するには「零相変流器(ZCT)」、地絡電圧を検知するには「零相電圧検出器(ZPD)」か「接地形計器用変圧器(EVT)」が必要になります。
- 無方向性(GR)であれば、零相変流器(ZCT)が必要。
- 方向性(DGR)であれば、零相変流器(ZCT)と零相電圧検出器(ZPD)か接地形計器用変圧器(EVT)が必要です。
零相変流器(ZCT)について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
零相電圧検出器(ZPD)について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
接地形計器用変圧器(EVT)について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
ちなみに、高圧需要家に設置してあるPASには、零相変流器(ZCT)と零相電圧検出器(ZPD)が内蔵されています。
無方向性と方向性の違い
先程から地絡継電器(GR)には無方向性と方向性があると説明してきましたが、どの様な違いがあるのでしょうか?
地絡が発生すると地絡点だけでなく、同一の配電線全ての箇所で地絡電流が流れます。この為、事故点ではない健全な回路でも地絡電流が流れ地絡継電器(GR)が動作する場合があります。
これを「もらい事故」と言います。もらい事故について詳しくは、こちらの記事を読んで下さい。
このもらい事故を防ぐのが方向性の地絡方向継電器(DGR)です。
無方向性では地絡電流の大きさのみで動作します。地絡方向継電器(DGR)では、地絡電圧も検知して電流と電圧の位相差で電流の方向を判断します。それにより構内の事故なのか、構外の事故なのかを判断して構外であれば動作しません。
まとめ
- 地絡継電器には無方向性と方向性がある
- 「GR」「DGR」「51G」「67」と呼ぶこともある
- 検知には零相変流器(ZCT)や零相電圧検出器(ZPD)が必要
- もらい事故を防ぐには方向性が必要
地絡継電器(GR)は高圧受電設備の保護継電器において、最も重要なものになります。キチンと目的などを理解しておきましょう。今後、各項目についてもう少し掘り下げて記事にしたいと思います。
この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。














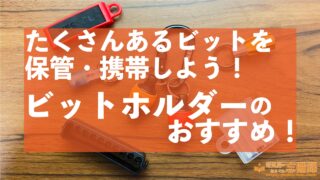




















コメント