どうもじんでんです。いきなりですが、電気の仕事に大事な道具って何でしょうか?
ドライバー、ペンチ、テスター、メガー色々な道具が思い浮かびますね。また電気の仕事といっても様々な職種があり、それぞれで使用する道具は大きく変わってきます。
しかし電気に感電しない、自分の身を守るはどれにも共通する事かと思います。電気は目に見えないし、匂いも音もしません。そんな電気が有るか無いかを判断する必要があります。
現場で簡単に、電気の有無を確認する道具として挙げられるのが検電器です。検電器は回路に接触させるだけで、電気の有無を確認できます。
今回はそんな検電器の選び方とおすすめを紹介します。
検電器とは?
電気屋にとって最も必要な道具とも言えるのが検電器です。
電気の作業は停電しての作業が原則です。なので電線等に触る前には、電気がきていないことを確認することが鉄則です。電気の有無を調べる為に検電器を使用します。
検電器の使い方
検電器を電気がきている部分にあてると、音や光で知らせてくれます。なのであてても音や光の反応がない場合は電気がきていないということになります。
電気の有無を調べる行為を「検電」と言います。
電気の有り無しを知る方法として、テスターによる電圧の測定なども有効です。しかしただ電気の有無を知りたいだけなら、検電器による確認が簡単です。
自分の命を守る為に行う検電ですので、できるだけ簡単に実施できるのが望ましいです。面倒だったりすると検電の行為自体を省略してしまう場合があるからです。
検電器の詳しい使い方については、こちらの記事で解説しています。
検電器の原理
検電器には、動作原理の違いでいくつかの種類があります。
- 電子回路式検電器
- ネオン発光式検電器
- 風車式検電器
- はく検電器
はく検電器は教育目的の実験用なので、実用はされていません。またネオン発光式検電器も現在では、需要が減っています。風車式検電器は特別高圧用として使用されるものなので、電気工事向けでは一般的には見かける事はありません。
よって電気工事で扱う一般的な検電器の殆どは、電子回路式検電器となります。
電子回路式検電器の原理を簡単に解説します。
人が検電器を持って電線に接触させると、人体を通して微弱な電流が流れます。この微弱な電流は1μA以下で、人体には何も影響が無いレベルです。
この電流が流れる回路は、検電器と人体の静電容量と、人体と大地の静電容量により構成されます。被覆の上からの検電では、更に電線の心線と検電器の間の静電容量により回路が構成されます。流れる電流は更に小さくなるので、感度を上げています。
検電器には握る部分が指定されていますが、この理由は上記の静電容量に関連します。握る部分の違いで静電容量の大きさが変わってくるので、検出感度を保つ為に握る部分が指定されています。
微弱な電流を電子回路で増幅して、音や光で充電状態を表現しています。
検電器の選び方
電気といっても交流や直流、電圧の大きさなど色々な種類があります。
それぞれに対応した検電器を選ぶ必要があります。どれにも対応する万能な検電器はありません。
ここでは、検電器を選ぶポイントをまとめました。
電圧の大きさから選ぶ
電気には電圧の大きさがあります。検電器にも使用できる電圧の下限値と上限値が決まっています。自分が作業する回路の電圧に適用できる検電器を選びましょう。
万が一これを間違えると、低すぎて検電器が動作しなかったり、高すぎて検電器を通して感電する場合もあります。怖いのは適用より下の電圧で動作せずに、電気がきていないと勘違いし感電することです。
数ある検電器の中には切替式で低圧~高圧まで幅広く対応するものもあります。一台でどのような場面でも使用できるメリットがあります。
しかし切り替えを忘れたりした場合は、先ほど述べたように勘違いが発生する可能性があるので個人的にはお勧めできません。可能な限り、低圧用と高圧用では分けて揃えることをお勧めします。
電気の種類から選ぶ
電気を2種類に分けると交流(AC)と直流(DC)に分けられます。
電気屋の多くの作業は交流回路だと思います。なので多くの検電器が交流のみの対応です。
直流回路で検電が必要な場合は専用の検電器を用意しましょう。
また最近は太陽光発電所の普及により直流回路が増えてきていますので、必要となることも多いでしょう。一般的な検電器では直流回路は検電できないので注意が必要です。
有電圧時の表現方法
検電器は電圧があれば、何らかの方法で知らせてくれます。多くは音と光で知らせてくれます。
特高用の一部の検電器は風車型と言って先の風車が回転して知らせてくれるものもあります。
検電器によっては光が見えにくかったり、音が小さかったりと分かりづらいものもあります。実際の現場では騒音があったりと状況が悪い場合がありますので、できる限りわかりやすい光(一部ではなく全体的に光る)や大きな音で知らせてくれる検電器を選びましょう。

常時スタンバイタイプか
検電器には、常時スタンバイタイプと呼ばれる検電器があります。
常時スタンバイタイプとは検電器本体に電源のON/OFFが無く、常に検電できる状態のものです。
常時スタンバイタイプではない検電器の場合、電源のONを忘れた場合に音や光が出ずに無電圧と勘違いしてしまう恐れがあります。それを考えると常時スタンバイタイプの方がヒューマンエラーを防止できます。
しかし常時スタンバイタイプは、比較して電池の持ちが悪いデメリットがあります。
またON/OFFタイプでは、無駄に電池を消耗しないようにオートパワーオフ機能があるものをおすすめします。
金属非接触タイプ
現在、低圧検電器では被覆の上からでも電圧を検知できる、金属非接触タイプの検電器が主流です。よく非接触タイプの検電器などとも呼ばれますが、非接触だと少し語弊があるかと思います。
検電器は基本、金属の露出部に接触させて反応を見ます。
検電する状況として、目の前の電線が無電圧で切ってもいいかを判断する為に検電します。すると電線は被覆に覆われているので、金属の露出部はありません。
すべて停電していれば、迷うことはありません。しかし一部だけ停電している場合は、充電している電線と停電している電線が混在している状況があります。
そんなときは被覆の上からでも検電可能な検電器を使うと判断ができます。
感度調整機能
前述の金属非接触タイプは、静電誘導によって電圧を検知しています。
しかし感度により検電対象外の電圧を検知して、停電しているのに検電器が反応してしまうことがあります。これを解消する為に、感度調整ができるタイプの検電器があります。
感度調整すれば、的確に対象回路の電気の有無を調べられます。
製品によって感度を2段階で調整できるものや、感度をダイヤルで無段階で調整できるものがあります。

金属非接触タイプを選ぶなら、感度調整機能があるものを選びましょう。
大きさで選ぶ
先ほどまでは仕様や技術的な観点でのポイントでしたが、これからは現場での使いやすさなどのポイントになります。
検電とは作業においてその都度、実施しなければなりません。作業をする前に検電、触る回路が変われば検電と何度もしなければいけません。そうなると常に身に着けておくのがいいでしょう。
低圧回路のみの作業であればポケットに入れておけるサイズ、高圧であれば腰道具のサックに収まるサイズがお勧めです。特高になると離れた位置からの検電が必要になるので携行できるものはあまりないかもしれませんが、伸縮式のものだと持ち運びが便利です。
携行に邪魔になるようなサイズを選んでしまうと、どうしても人は省略しようとしてしまいます。『ブレーカーを切ったから絶対に電気はきていない』など状況や慣れから電気の有無を判断した結果、勘違いによる感電となってしまいます。
このようなことをなくす為にも、電圧区分に応じた検電器を複数購入することをお勧めします。
おすすめ低圧検電器
ここまで検電器の選び方を紹介しましたが、おすすめの低圧検電器を紹介しています。
HIOKIの3481
HIOKIの3481は、最も現場でよく見る低圧検電器です。
人気なだけあって、迷ったらこれを選んでおけば間違いありません。基本的なポイントは押さえてあります。
しかし常時スタンバイタイプではないのが残念なポイントです。
| 項目 | 対応 | 備考 |
|---|---|---|
| 適用電圧 | AC40V~600V | |
| 常時スタンバイ | × | |
| 金属非接触 | 〇 | |
| 感度調節機能 | 〇 | 無段階 |
| CAT対応 | CAT IV 600V |
詳しくは3481のレビュー記事をご覧ください。
HASEGAWAのHTE-610L
HASEGAWAのHTE-610Lは、検電器で有名なメーカーである長谷川電機工業の低圧検電器です。
特徴は電源のON、OFFが無く常時スタンバイ方式を採用しています。電源入れ忘れによるヒューマンエラーを防止できます。感度調節等の基本的な機能は押さえてあり、一番おすすめできる検電器です。
| 項目 | 対応 | 備考 |
|---|---|---|
| 適用電圧 | AC50〜600V | |
| 常時スタンバイ | 〇 | |
| 金属非接触 | 〇 | |
| 感度調節機能 | 〇 | 無段階 |
| CAT対応 | × |
詳しくは、HTE-610Lのレビュー記事をご覧ください。
共立電気計器のKEW5711
共立電気計器のKEW5711の特徴は、電池が珍しく乾電池です。
ほとんどの検電器がボタン電池で入手性が悪いですが、KEW5711なら乾電池なので解決してくれます。その分、本体サイズが大きいのがデメリットです。
| 項目 | 対応 | 備考 |
|---|---|---|
| 適用電圧 | AC20~1000V | |
| 常時スタンバイ | 〇 | |
| 金属非接触 | 〇 | |
| 感度調節機能 | 〇 | 2段階 |
| CAT対応 | CAT Ⅳ 600V CAT Ⅲ 1000V |
詳しくはKEW5711のレビュー記事をご覧ください。
FLUKEの1AC-A2-Ⅱ
1AC-A2-Ⅱは、計測器メーカーで歴史のあるフルークの検電器です。
フルークはアメリカの企業なので、製品も世界を相手にしたものとなっています。
日本メーカーのような、ありがたいオマケ機能はないですが、安全性に特化していると言えるでしょう。適応電圧が高いのが特徴です。
| 項目 | 対応 | 備考 |
|---|---|---|
| 適用電圧 | AC90V〜1000V | |
| 常時スタンバイ | × | |
| 金属非接触 | 〇 | |
| 感度調節機能 | × | |
| CAT対応 | CAT Ⅳ 1000V |
詳しくは1AC-A2-Ⅱのレビュー記事をご覧ください。
共立電気計器 KEW5712
共立電気計器のKEW5712は、直流にも対応した低圧用検電器です。
多くの検電器が交流にしか対応していませんが、KEW5712は交流も直流も対応しています。太陽電池発電設備の普及で直流回路も増えてきました。
太陽電池発電設備の保守管理をする人にはおすすめです。
| 項目 | 対応 | 備考 |
|---|---|---|
| 適用電圧 | AC80~600V DC40~750V | |
| 常時スタンバイ | 〇 | 切替スイッチが あるので注意 |
| 金属非接触 | 〇 | |
| 感度調節機能 | 〇 | |
| CAT対応 | × |
詳しくはKEW5712のレビュー記事をご覧ください。
おすすめの高圧検電器
おすすめの高圧検電器を紹介します。
HASEGAWAのHSG-6
HASEGAWAのHSG-6は、高圧検電器の中でも軽量・小型の検電器です。
高圧検電器を常に携行する人におすすめです。コンパクトなので邪魔になりにくく、煩わしさが軽減できます。
HASEGAWAのHSN-6A1
HASEGAWAのHSN-6A1は、交流と直流どちらにも対応した高圧検電器です。
高圧機器の絶縁耐力試験を想定した製品となっており、「AC10.5kV・DC21kVまで使用可能」と謳ってあります。これ1本で交流及び直流の絶縁耐力試験の検電に対応できます。
検電器に関するQ&A
検電器に関する様々な疑問をまとめました。
- Q検電器とテスターの違いは?
- A
検電器は電気の有無を調べるものです。対してテスターは電気が何ボルトなのかを調べるものです。
検電器では対象の回路が充電されているのか、停電しているのかしか分かりません。回路の電圧が100Vなのか200Vなのかを調べるには、テスターが必要です。
- Q検電器は必要ですか?
- A
検電器は停電していることの確認をする道具として、必須のアイテムです。
電気工事業の業務の適正化に関する法律では、電気工事事業者は検電器を備え付けることが義務付けられています。また労働安全衛生規則でも、回路が停電したことを検電器にて確認することとなっています。
- Q検電器はどこで購入できますか?
- A
低圧用の検電器は、身近なところではホームセンターでも取り扱っています。Amazonなどのネットショップでも購入可能です。
まとめ
- 使用する回路の電圧にあうものを選ぼう。
- 多くは交流にのみ対応。直流が必要なら対応しているものを選ぼう。
- 電圧区分で使い分けよう。
- 有電圧時はできる限り大きな音や分かりやすい光で知らせてくれるものを選ぼう。
以上、検電器の選び方のポイントでした。
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

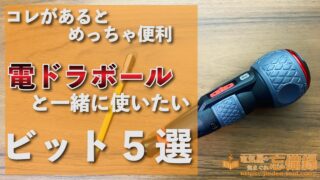


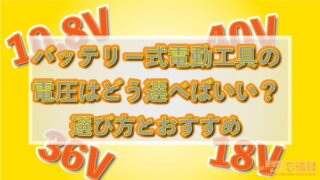




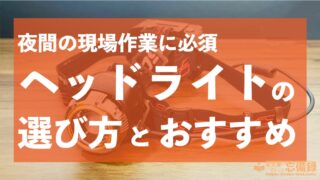



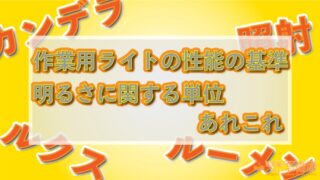





















コメント